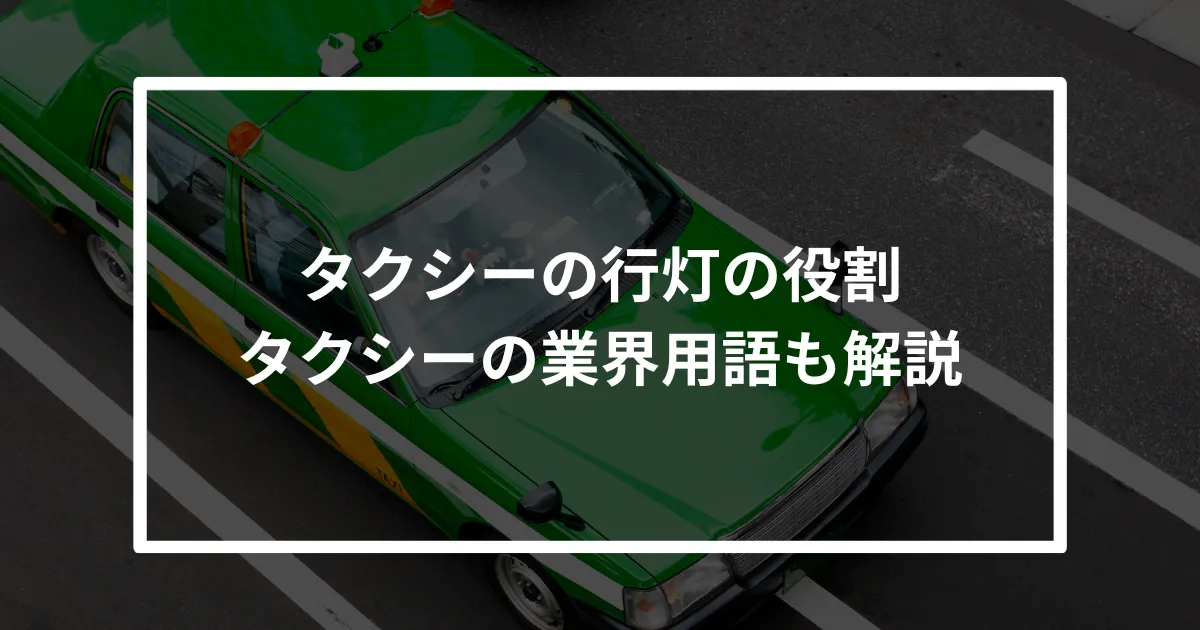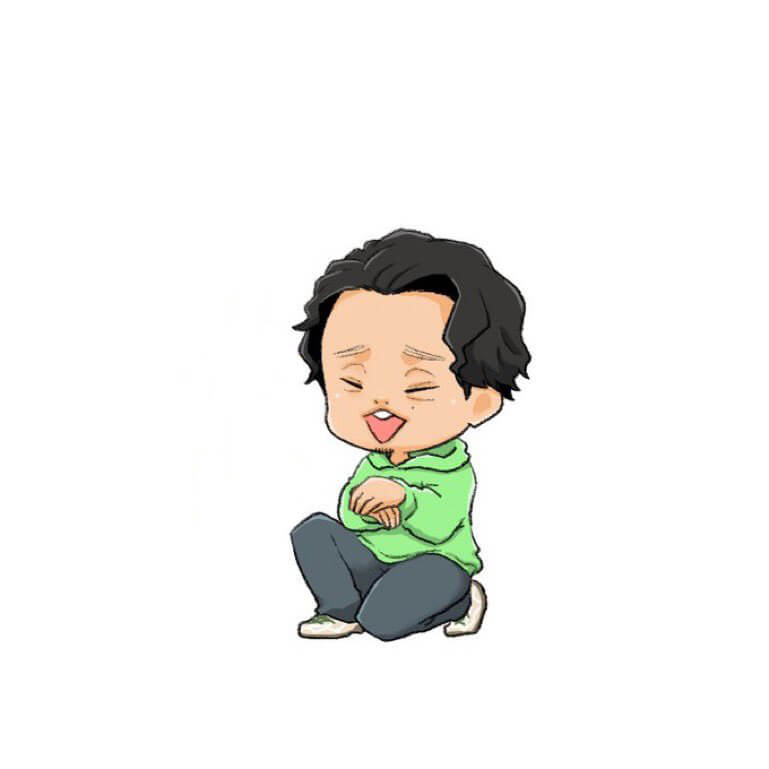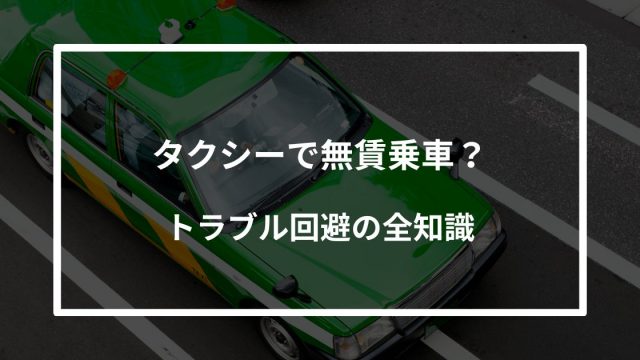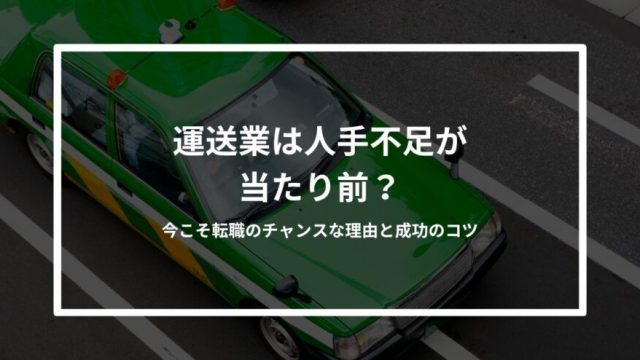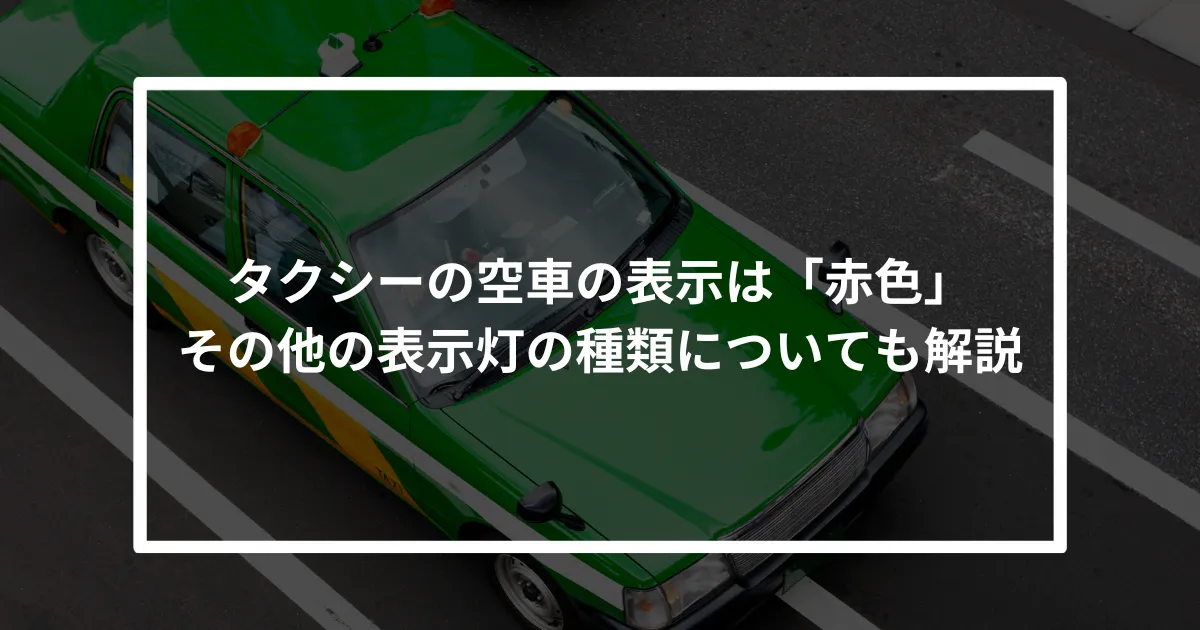タクシーの行灯の役割ってなんだろう?
タクシーの業界用語が知りたい!
安全運転のために意識すべきことが知りたい!
ご紹介する「タクシーの業界用語」を読むと、入社した際に頭ひとつ抜けて仕事ができますよ!
まずは「タクシーの行灯」の概要をまとめておりますので、ぜひ読み進めてください!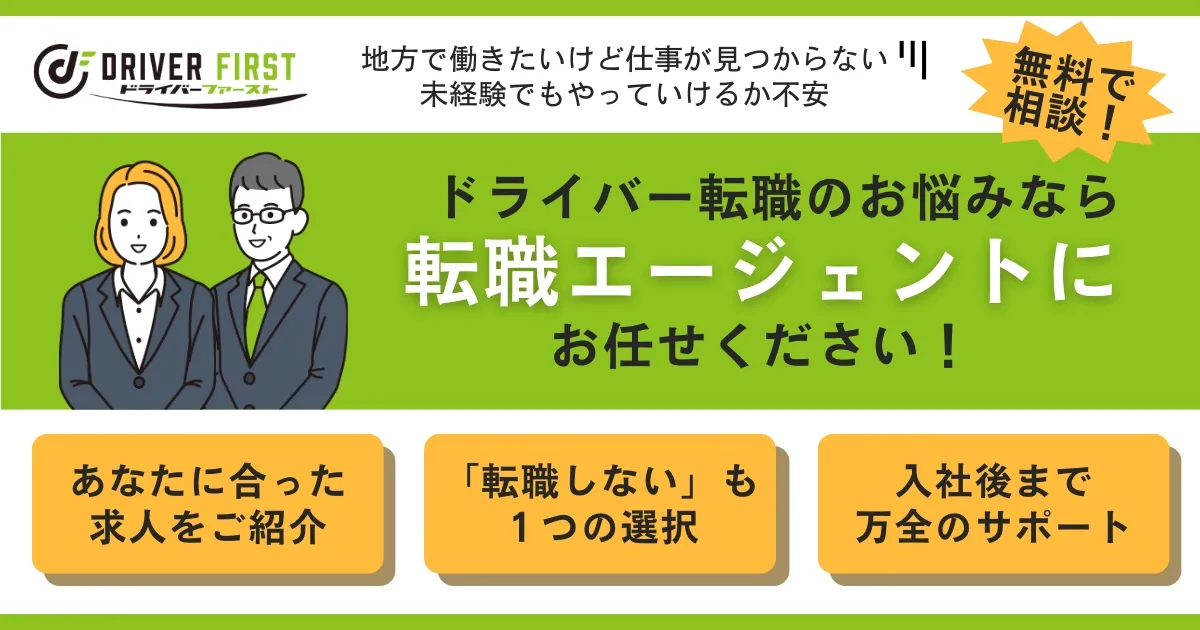
目次
タクシーの行灯(あんどん)とは

引用:タクシー「行灯」誕生の背景 元々「社名表示」は目的じゃなかった 老舗メーカーに聞く
タクシーの屋根にある表示灯は、「行灯(あんどん)」と呼ばれます。
これは、タクシーの車体の上部についている、会社名を表示するランプのことです。
行灯は、昔ながらの照明のひとつです。
木や金属のわくに和紙をはり、風で火が消えないように工夫されています。
今では、火の代わりに電球が使われるようになりました。 提灯は、細い竹をまるく筒状にした、持ち運びできる照明です。
お祭りや屋台などで、見かけることが多いのではないでしょうか。
関連記事:タクシー運転手の仕事内容|タクシー運転手が向いている人の特徴も紹介
タクシーの行灯の役割

タクシーの行灯の役割は以下のとおりです。
- 緊急性を知らせる
- 一般車両と区別するため
- 違法タクシーを防ぐため
順番に解説します。
緊急性を知らせる
タクシーで強盗などの事件が起きた際、行灯を赤く点滅させ、まわりに緊急事態を知らせる場合があります。
ふだんは白色のランプですが、赤く光っていれば異常事態です。
もし、赤く点滅するタクシーを見かけたときは、ためらわずに110番通報してください。
一般車両と区別するため
タクシーが行灯をつける理由は、交通量が多い都会などでも、すぐに見つけられるようにするためです。
以前は「タクシーといえばこの形」という共通のイメージがありました。
しかし、規制緩和により様々な車種が使われるようになり、外見だけではタクシーと判別しづらくなっています。
そのため、最近では行灯がついているかどうかが、タクシーを見分けるポイントといえるでしょう。
違法タクシーを防ぐため
タクシーは、行灯の装着が法律で義務づけられています。
一般の車には、つけることが許可されていません。 そもそも、タクシーのような旅客運送事業は、国から許可を得た会社や個人だけが行えます。
許可なく運送事業を行うと、違法行為として厳しく罰せられます。
これは、タクシー事業者のかたの利益を守り、お客様の安全を確保するためのルールです。
運転技術が十分でない一般のかたが、自由に旅客運送を行うリスクを防ぎます。 行灯は、国から許可されたタクシーの目印です。
利用者は安心して乗車でき、行灯のない違法タクシーは利用されにくくなります。
このように、行灯は違法タクシーの利用者を増やさない役割も果たしているのです。
関連記事:タクシー会社へ転職するための相談内容|ドライバーに向いている人の特徴も解説
タクシーの業界用語

タクシーの業界用語は以下のとおりです。
- 流し
- 着発
- 付け待ち
- オバケ
- コロ
- 現着
- 圏外
順番に解説します。
流し
タクシーの「流し」とは、街なかを走りながら、お客様をさがす営業方法です。
空車で走るタクシーを、道でひろった経験があるかたも多いでしょう。
流し営業のタクシーは、営業エリア内なら、どこでもお客様を乗せられるメリットがあります。
着発
お客様を降ろした場所で、すぐ別のお客様が乗車された際に使う言葉が「着発」です。
「今日は着発が2回あった」のように使います。
付け待ち
タクシーが駅やホテル、病院などの乗り場で、順番にお客様が乗るのを待つことを指します。
オバケ
遠くまでタクシーを利用されるお客様のことです。
予想外の時間や場所で、非常に長い距離を利用するお客様を乗せた場合、「駅付けでお化けが出た」などと言うことがあります。
コロ
近距離を利用されるお客様を「コロ」と呼びます。
「タイヤが少し転がるくらいの距離のお客様」という意味です。
もちろん、短い距離のご利用も大歓迎だそうです。 例:「今日は、コロが多かった」
現着
「現着」は、現場到着を短くした言葉です。 お客様がお呼びになった場所に到着した際、無線センターへ連絡を入れます。
「ただいま現着しました」といった使い方をします。
圏外
タクシー会社は「営業区域」という決められたエリア内でのみ、営業ができます。この区域外で営業することは禁止です。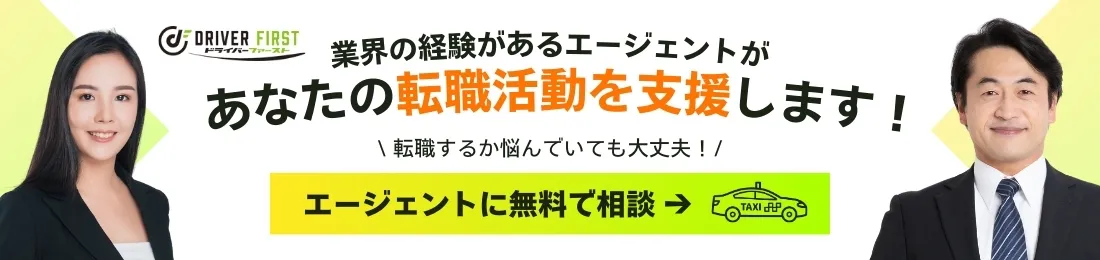
【タクシードライバー】安全運転のために意識すべきこと

安全運転のために意識すべきことは以下のとおりです。
- 停車する際に周囲を注意する
- ドアを閉めるタイミング
- シートベルトの着用の依頼
- お客様との会話
- 適度な休憩
順番に解説します。
停車する際に周囲を注意する
タクシー運転手が事故を起こしやすいのは、お客様の乗り降りの時です。注意しましょう。
お客様の要望を優先するあまり、周りをよく見ないままタクシーを停めてしまう運転手もいます。
その結果、後ろの車に追突されたり、まわりの交通の邪魔になったりする危険性が高まるでしょう。
また、前方に乗車しそうなお客様を見つけた際、反射的にブレーキを踏むのも良くありません。
ドアを閉めるタイミング
車を道路の左側に寄せて停めたとしても、安心はできません。
自転車やバイクが左側を通ろうとする時にドアを開け、事故になることも考えられます。
運転中は周りに気を配っていても、お客様が乗り降りする際は、対応に気を取られて注意不足になる場合があるでしょう。
そのような時に、自転車などが左後ろから来ていると、ドアを開けた際に事故が起きるかもしれません。
シートベルトの着用の依頼
道路交通法が変わり、今は後部座席のかたもシートベルトをしなければなりません。
運転中にシートベルトを着用しないと、「座席ベルト装着義務」に違反することになります。
しかし、それ以上に、シートベルトはお客様の安全を守るための大切なものです。
万が一、事故が起きても、被害を小さくする効果があります。
お客様の中には、シートベルトを嫌がるかたもいるでしょう。
しかし、丁寧にお願いし、必ず着用してもらうことが大切です。
お客様との会話
走行中にお客様に楽しんでいただくため、話しかけられたら積極的に応じ、会話を楽しむことも接客の一つです。
しかし、タクシー運転手の目的は、あくまでお客様を安全に目的地へ送り届けることです。
会話に夢中になりすぎて、運転がおろそかになっては意味がありません。
お客様から話しかけられたら無視をするのはいけません。ですが、自分から話すことはほどほどにし、常に安全運転を心がけましょう。
適度な休憩
ベテランのタクシー運転手であっても、長時間運転をすれば体力や注意力が落ち、事故の危険性が高まります。
特にタクシー運転手は、隔日勤務で働くかたが多く、一度の運転が長くなりがちです。
また、次々にお客様を見つけ、休みなく走行する場合もあるでしょう。しかし、事故を起こすと損失はさらに大きくなります。
そのため、しっかり働くためにも、適度な休憩を取り、常に安全運転ができるよう、自分で体調管理をすることが大切です。
まとめ
タクシーの屋根にある「行灯(あんどん)」は、会社名を示す照明で、昔の照明器具に由来します。
行灯には、お客様がタクシーを見つけやすくする、緊急時に周囲に知らせる、違法な白タクと区別するという大切な役割があります。
私たちタクシー運転手は、行灯を正しく点灯し、安全運転を心がけています。
街でタクシーを探す際は、この行灯を目印にしてください。また、赤く点滅している場合は緊急事態ですので、110番通報をお願いします。