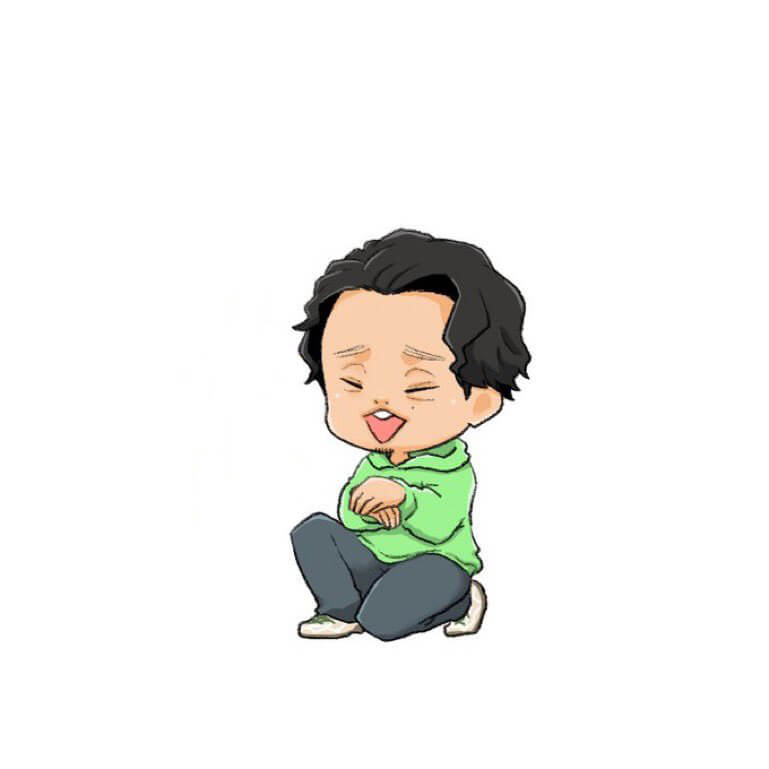「タクシー料金はどのように決まるのかな」
本記事では、タクシー料金の目安と併せて、追加料金についても解説します。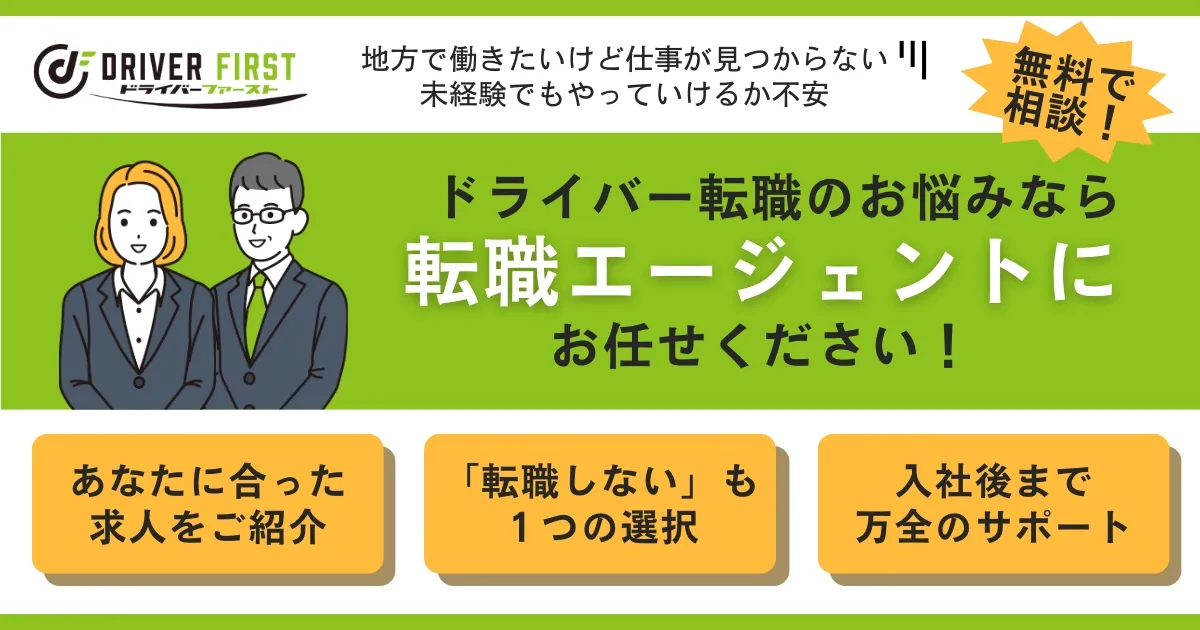
目次
タクシー料金の目安を知るには仕組みの理解が大切

タクシーに乗車した瞬間、料金メーターは稼働を開始しますが、出発点から料金が積み上がるのは一定の初乗り運賃からです。
この初乗り運賃は、乗車開始からタクシー会社や地域に定められた特定の距離までをカバーする固定料金です。
例を挙げると、初乗り距離が1.052kmで420円の設定の場合、この距離内であれば距離に関係なく同額が課金されます。
1.052kmを超えると、加算運賃が適用され、料金が上乗せされていきます。
タクシーの料金体系は「時間距離併用型」と称され、走行距離と時間の経過に応じて料金が増加していきます。
多くの人が走行距離に応じた加算を認識していますが、低速走行や停止時にも時間経過に応じた加算があることは意外と知られていません。
理解しておくことで、無駄な料金増加を避けることが可能です。具体的には、233m走行ごと、または10km/h以下で85秒経過ごとに80円が加算されるのが一般的な設定ですが、これはタクシー会社や地域によって異なります。
タクシー料金の仕組みを把握することは、予期せぬ高額な料金に驚くことを避け、賢く移動するための鍵となります。
関連記事:【結論】タクシー運転手ボーナスはある!給与体系や仕組みを解説
タクシー10km利用時の目安料金

タクシー10km利用時の目安料金は以下のとおりです。
- 待機時間がない場合
- 10分間の待機時間が発生した場合
- 配車予約をした場合
- 深夜または早朝の場合
順番に解説します。
待機時間がない場合
タクシーを利用する際、多くの人が気になるのが最終的な料金です。
特に待機料金が発生しない場合、料金の計算はよりシンプルになります。ここでは、10kmの移動を例に、タクシー料金をどのように計算するかを解説します。
まず、タクシーの初乗り距離が1.052kmで、その間の運賃が420円であるとします。
この距離を超えた場合、追加の距離に対して加算運賃が適用されます。加算運賃が適用される距離は、総走行距離から初乗り距離を差し引いた距離、つまり10kmから1.052kmを引いた8.948kmです。
この加算距離を、タクシー会社が定める加算距離単位(この例では0.233kmごと)で割ることで、加算運賃が何回適用されるかを計算できます。この場合、8.948kmを0.233kmで割ると約39回の加算が必要となります。
加算運賃が80円の場合、この加算回数を乗じて加算運賃総額を算出します。
したがって、初乗り運賃420円に39回分の加算運賃(80円×39回)を加えた合計が、待機料金なしでのタクシー料金となります。
この計算方法を理解することで、タクシー利用時の予算計画がより容易になります。
関連記事:タクシー運転手に転職する方法|転職する人の特徴も紹介
10分間の待機時間が発生した場合
タクシーの利用時には、信号待ちやコンビニへの立ち寄りなどの待機時間も料金に影響します。たとえば、合計待機時間が10分の場合、以下の計算式で料金を算出できます。
まず、走行距離から初乗り距離を差し引き、その後、加算距離を距離加算運賃の計上回数で割ります。
そして、初乗り運賃に距離加算運賃を加えて距離に関する料金を算出します。
次に、待機時間に関する料金を算出します。待機時間の回数は、合計待機時間を85秒(タクシーの待機時間の基準秒数)で割った数になります。
この回数を時間加算運賃に掛けて、時間に関する料金を求めます。
最後に、距離に関する料金と時間に関する料金を合算して、最終的なタクシー料金を算出します。
この方法に基づき、10分の待機時間を含む場合のタクシー料金は、初乗り運賃に加えて距離と時間に関する追加料金を合算したものになります。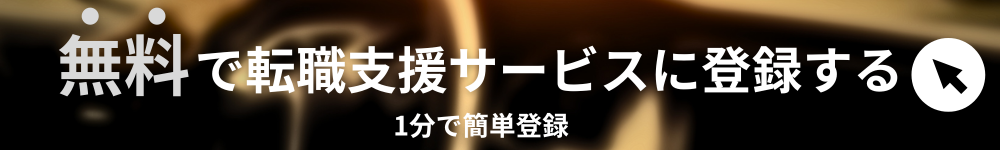
配車予約をした場合
タクシーを利用する際には、特定の時間や距離に基づいて料金が計算されます。たとえば、10kmの走行をする場合、以下の計算式を用いて料金を算出できます。
まず、走行距離から初乗り距離を差し引き、その後、加算距離を距離加算運賃の計上回数で割ります。
そして、初乗り運賃に距離加算運賃を加えて距離に関する料金を算出します。
さらに、迎車料金や予約料金などの追加料金を加えて、最終的なタクシー料金を算出します。
この方法に基づき、10kmの走行をする場合のタクシー料金は、初乗り運賃に加えて距離に関する追加料金、そして迎車料金や予約料金を合算したものになります。
深夜または早朝の場合
タクシーを深夜や早朝に利用する際には、通常の料金に比べて割増料金が適用されます。
例えば、深夜早朝割増が適用される時間帯に10kmの走行をする場合、以下の計算式を使用して料金を算出できます。
まず、深夜早朝割増時の初乗距離と加算距離を計算します。初乗距離と加算距離を考慮して、走行距離から初乗り距離を差し引き、その後、加算距離を距離加算運賃の計上回数で割ります。
そして、初乗り運賃に距離加算運賃を加えて距離に関する料金を算出します。
この方法に基づき、深夜早朝割増が適用される時間帯に10kmの走行をする場合のタクシー料金は、割増料金を含めた初乗り運賃に距離に関する追加料金を加えて算出されます。
関連記事:タクシーの待機料金を抑える3つの方法|発生するケースも詳しく解説
タクシーの追加料金

タクシーの追加料金は以下のとおりです。
- 迎車料金
- 深夜・早朝の割増
- 予約料金
- 待機料金
- 冬季割増料金
順番に解説します。
迎車料金
タクシーを特定の場所に呼び寄せる際にかかる料金は、「迎車料金」と呼ばれます。
一般的には数百円程度ですが、一部の会社では無料サービスを提供している場合もあります。
一部のタクシー会社では、「スリップ制」を採用しています。
これは、迎車に向かうタイミングでメーターを起動し、初乗り運賃の一部が迎車料金として課金される制度です。
迎車距離が長い場合には、メーターが一旦停止し、乗車後に再度メーターが起動する仕組みで、迎車料金が適正な範囲に抑えられるようになっています。
深夜・早朝の割増
タクシーの料金は、一般的には夜間の時間帯である22時から翌5時まで、通常の料金に比べて2割増しとなります。
夜間料金が適用される時間帯には、メーターが上がるために必要な距離が通常よりも短く設定されています。
これにより、日中よりも早く距離が加算される仕組みになっています。
予約料金
予約料金は、特定の時間を指定してタクシーの配車を依頼した際にかかる料金です。通常の即時配車とは異なり、希望の時間帯を指定する点が特徴です。
タクシーの配車予約は事前に申し込む必要があり、予約可能な枠数が限られていることが一般的です。
そのため、日時指定をする場合には、早めに予約をすることが重要です。
待機料金
待機料金は、タクシーを呼んだにもかかわらず、呼んだ側の都合でタクシーを待機させた際に発生する料金です。
通常、5分以上待機させるとメーターが回り始め、その後は各タクシー会社によって異なりますが、一般的には90秒ごとに追加料金が発生します。
冬季割増料金
冬季割増料金は、降雪や路面凍結などにより運転が困難な状況下でのタクシー利用時に適用される料金制度です。
通常の料金に比べて約2割増しとなることが一般的です。
この割増料金は、主に北海道や東北地方など積雪が多い地域で、12月から3月頃までの冬季期間に適用されます。
まとめ【タクシー料金の目安を理解しましょう】
今回は、タクシー料金の目安と併せて、追加料金についても解説しました。
タクシーの追加料金は以下のとおりです。
- 迎車料金
- 深夜・早朝の割増
- 予約料金
- 待機料金
- 冬季割増料金
「運転が好き!」「話すのが好き!」「気配りが得意!」こんな人は、タクシードライバーが向いています。
ドライバーファーストなら専任スタッフがプロの目線からあなたの転職をサポートいたします。
また、タクシードライバー未経験でも応募可能な求人もたくさんあるので、初めての方でも安心して就職できます。
興味がある方は、お気軽に「転職支援サービス」をご利用ください。